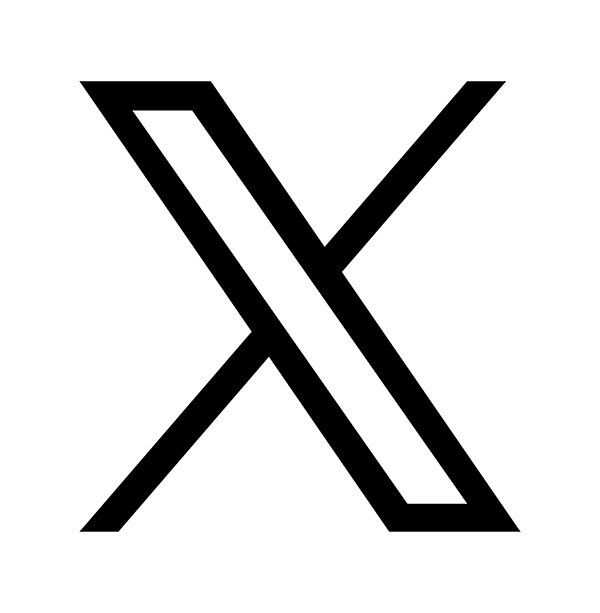結城 靖博 (ゆうき やすひろ)さんの自己紹介
新潟県三条市生まれ。155年もの歴史を誇る老舗料亭「遊亀楼 魚兵(ゆうきろう うおひょう)」の代表取締役です。その他、ニートや引きこもりの方々に就労機会を提供する会社「Connection」、まちづくり会社「株式会社 燕三条」の代表も務めます。「自分が楽しいから、やりたいから」という想いでさまざまな地域活動も行っています。お願いされたら断れない性格というのもあり、どんどん増えていくんですよ(笑)
PROLOGUE

普段何気なく使っている包丁、スプーンやフォークなどのカトラリー。毎日手にするものがどこで、誰が、どのように作っているのかなんて、あまり考えたことはないかもしれません。ですが、ものづくりの裏側を知る機会があったなら…学んだり体験したり、普段はなかなか立ち入ることのない工場に潜入できたら…想像するだけでなんだかワクワクしませんか?
そんな心踊るイベントが、今年も新潟県燕三条地域で開催されます。それが「燕三条 工場の祭典2025(以下、工場の祭典)」です。

「工場の祭典」は、普段は見ることのできない工場の扉を一斉に一般開放し、ものづくりの現場を見せてくれる年に一度のオープンファクトリーイベント。今年で13回目を迎え、開催期間中は全国ひいては世界から何万人もの人々が訪れます。新潟県民の皆さんは「知っている」「行ったことがある」という方も、多いのではないでしょうか。
2025年は「ものづくりで繋げ」をテーマに、10月2日(木)から5日(日)まで4日間の開催。燕市や三条市全域及び周辺地域、なんと約130か所で開催される予定です。
今回、道の駅国上の林美樹駅長にご紹介いただきお会いしたのは、同イベントを主催している「燕三条 工場の祭典実行委員会」で専務理事を務める、結城 靖博(ゆうき やすひろ)さんです。

結城さんは三条市で3つの会社を経営する傍ら、三条商工会議所青年部、三条凧協会、燕三条匠の守護者プロジェクトなど、その活躍は多岐にわたります。仕事に加え、数々の地域活動にも励んでいるスーパーマンのような方なんです!
今回は結城さんに今年の工場の祭典の見どころやこれまでの変遷、今後の展望をお聞きしてきました。これを読んだら…きっと工場の祭典に行ってみたくなりますよ!
INTERVIEW
日本が誇るものづくりの現場を体感

燕三条地域は、燕市と三条市を合わせた地域のことで、金属加工技術で世界的に知られる「ものづくりのまち」です。包丁や鍋などの金属洋食器、大工道具、農機具など、日本の生活を支える製品の多くがこの地域で作られています。
「工場の祭典では、地域の工場が一斉に扉を開き、職人たちの技術を間近で見学できます。また、工場を巡りながら、製品ができあがる過程を見学したり、職人さんから直接話を聞いたり、実際にものづくり体験をしたりすることができるのが魅力ですね。13回目の開催となる今年、注目していただきたいポイントは3つあります。まず1つ目は、今年は過去最多となる132社が参加予定です。より色々な業種や技術に触れる機会が増えて、初めての方もリピーターの方も存分に楽しんでいただけると思います」と結城さんは話します。
なお、昨年の参加企業は109社で、来場者は3万8,592人。今年は約4万2,000人の来場者数を目指して、結城さんら実行委員会は国内外へのPR活動にも力を入れてきました。

続いて、2つ目の魅力は”ツアー”を大幅に拡充したこと。「今年は30本ぐらいのツアーを計画しています。小学生向けのツアー、バイヤー向けのツアー、包丁を作る工程を追うツアーなど、様々な切り口でものづくりの現場を体験できる企画が目白押しです」
ツアーに参加すればJR燕三条駅を発着として、自分の興味関心に合わせた工場を効率よく巡ることができるんです。これはいいですね!

そして3つ目が、参加地域の拡大です。従来の燕市や三条市に加えて、今年は加茂市や田上町の行政にも声をかけ、広域での産業観光都市を目指す取り組みが始まりました。
「燕三条って宿泊施設が少ないんです。せっかく4万人近くの人たちが来てくれるのだから、弥彦や田上の温泉施設や各地の道の駅との連携を図ることで、来場者にゆっくりと滞在してもらい、より充実した体験を提供したいと考えています」と語る結城さん。その背景には、これまでの来場者の滞在時間に課題がありました。
過去の来場者データでは、平均的な工場見学数は約1.5社。せっかく遠方から来場しても日帰りで帰ってしまう人が多い実状がありました。「1泊してもらえれば、翌日の午前中にもう1社多く工場を見て帰ることができる」と、産業観光として経済効果の向上も期待しています。
次世代に繋ぐオープンファクトリー
「産業観光」は、実際に稼働している工場や職人の技術を見学する観光のこと。景色や歴史的建造物を見て回る従来の観光とは異なり、その地域の産業や文化を深く理解することができるのが魅力です。
全国に約70カ所のオープンファクトリーイベントがある中で、燕三条の工場の祭典は年間4万人を動員する規模まで成長し、産業観光の先駆けとして全国から注目を集めています。

2013年からスタートした工場の祭典は、最初の10年間は行政が主導。東京のディレクターチームも入り「ピンクストライプ」というデザインで10年間続けてきました。そして11年目以降、運営を第一世代から第二世代へバトンタッチすることに。そこで白羽の矢が立ったのが、結城さんが当時会長を務めていた三条商工会議所青年部でした。

「今後の運営を三条商工会議所青年部でできないかという話をいただいたんです。それから私が燕市の商工会議所にも声をかけ、両市の青年部から出向者を出し合う形で、新たな実行委員会を発足しました。工場の祭典をさらに次世代へ繋いでいくための新体制です」
この世代交代は、全国のオープンファクトリーイベントが直面している共通の課題だと結城さんは言います。工場の祭典も例外ではなく、紆余曲折を経て現在の形に行き着き、今年は新体制になって2年目を迎えました。
「三条商工会議所青年部は全国組織に加盟せず、予算と人材をすべて地域に投入するという伝統を持っています。2年連続で同じ事業をしないという決まりがあり、常に新たな取り組みで自己研鑽をする『ベンチャー集団』のような組織なんです。この体質が、工場の祭典の運営にも活かせていると思います」と結城さん。
燕商工会議所青年部とともにお互いの良さを活かしながら、工場の祭典に新しい風を吹き込んでいます。
工場見学から産業観光としての魅力づくりへ

次の10年間に向けて歩みだした結城さんら実行委員会メンバー。これまでの「燕三条をものづくりの聖地にする」という目標から、「日本一の産業観光都市を目指す」ことをビジョンに掲げ、より具体的で明確な方向性を示そうとしています。
「日本一の産業観光都市にするためには、単に工場を見学するだけでなく、宿泊、グルメ、温泉、文化体験などを組み合わせた総合的な魅力づくりが不可欠です。ものづくりを見たいけれど、さらにおいしいグルメがあって、宿泊施設があって、温泉もあるんだとなれば、行ってみたいという機運がさらに高まるはずです」

工場の祭典は、単なる地域イベントを超えて、日本の産業観光のモデルケースとなる可能性を秘めています。ものづくりの現場を間近で体験し、職人の技術と情熱に触れることで、きっと新しい発見と感動が待っているはずです。10月の開催に向けて、燕三条の工場の扉が今年も開かれようとしています。
ちなみに、ごっつぉLIFE編集部である新潟県三条地域振興局も工場の祭典に参加し、ものづくりの達人として認定された「にいがた県央マイスター」らとともに、祭典を盛り上げます。ぜひ遊びに来てくださいね!
次回は、結城さんご自身にスポットを当て、3つの会社経営のこと、また数々の地域活動に励むパワーの源についてお話を伺ってきました。お楽しみに!